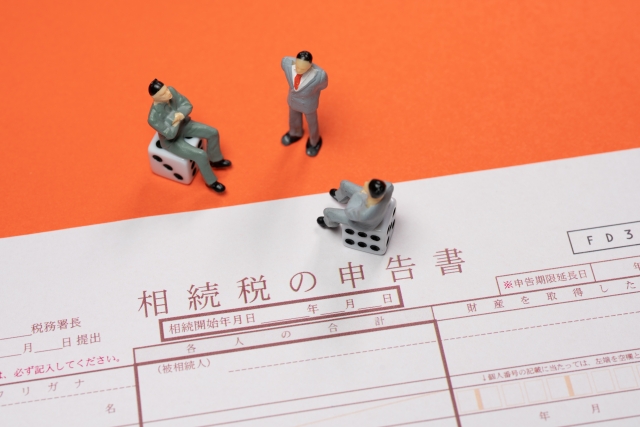
相続財産のうち、不動産は相続税計算において特に重要な要素です。
しかし、土地や建物の評価を適切に行わなかったことで、本来よりも高い評価額が算出され、結果的に過大な相続税を納付する事例があります。
本記事では、実際の失敗事例を基に、不動産評価の重要性と具体的な対策を解説します。
事例紹介:自宅土地を路線価のみで評価し、評価過大に
相続財産の大半が自宅の土地と建物だったAさん。相続税申告の際、税務署のホームページで調べた路線価をもとに土地の評価額を算出しました。
特例や個別事情は考慮せず、「路線価×面積」という単純計算だけで評価した結果、実際の利用状況よりも2割以上高い評価額となり、過大な相続税を納付してしまいました。
その後、相続に詳しい税理士に相談したところ、土地の一部が私道負担部分であることや、がけ地や不整形地であることが判明。
これらの補正を適用すれば、本来の評価額は約3割減額されることがわかりましたが、すでに申告・納税を終えており、更正の請求にも期限が過ぎていたため、結果的に過大納付分は取り戻せませんでした。
失敗の原因:不動産評価に関する専門知識の欠如
この事例の最大の失敗要因は、不動産評価の専門知識が不足していたことです。
土地の相続税評価は、単純に「路線価×面積」で求めるものではなく、以下のような個別要因を適切に反映させる必要があります。
主な評価減要素
- 不整形地補正(変形地や極端に狭い土地など)
- 私道負担部分の控除(建築基準法上の接道義務に関わる部分)
- がけ地補正(高低差がある土地の利用制限)
- セットバック(道路後退部分の評価減)
- 貸家建付地評価(賃貸物件が建っている場合の評価減)
これらの要素を無視して画一的に評価すると、本来よりも高い評価額になり、結果として不要な相続税負担が生じます。
税務署は過大申告を訂正しない
税務署は、申告漏れや過少申告には厳しく対応しますが、過大申告については納税者自身が更正の請求を行わない限り、是正してもらえません。
しかも、更正の請求には原則として法定申告期限から5年以内という期限があります。
この期限を過ぎると、明らかな評価ミスでも税額を減らすことはできません。
対策:不動産評価は必ず専門家に依頼
不動産評価は、相続税申告の中でも最も専門性の高い分野の一つです。
土地の形状、周辺環境、法的規制など、多くの要素を総合的に評価する必要があるため、
以下の対策を講じることが不可欠です。
相続開始後、速やかに現地調査を実施
まずは相続財産となる不動産について、現地調査を行います。
土地の形状や高低差、周辺道路との関係などを細かくチェックし、図面や写真を保存しておくことで、正確な評価の基礎資料とします。
不動産評価に精通した税理士や不動産鑑定士に依頼
相続税申告を依頼する税理士は、不動産評価に強い専門家を選ぶことが重要です。
必要に応じて不動産鑑定士の評価も依頼し、評価減要素を漏れなく反映させることで、適正な評価額を算出します。
評価方法を記録・保存
税務署からの調査や問い合わせに備え、不動産評価の際に使用した補正率や評価根拠を文書化し、申告書とともに保存しておくことが推奨されます。
これにより、税務調査の際にもスムーズに説明が可能です。
まとめ
相続財産に不動産が含まれる場合、不動産評価の適正性が相続税額に大きく影響します。
特に、個別事情を反映しない画一的な評価は、過大な税負担に直結します。
過大申告を防ぐためにも、相続税申告の段階から不動産評価に強い専門家に依頼し、適正な評価と税額計算を行うことが不可欠です。