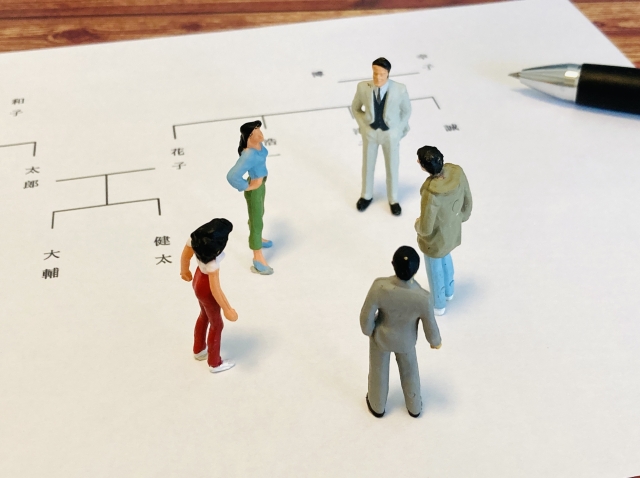相続の手続きを進めるときに、まず必要なのが「相続人はだれか」をはっきりさせることです。でも、戸籍の取り方や見方がむずかしそうで、不安に感じる人も多いでしょう。
この記事では、相続人を調べる手順を5つのステップと具体的な事例に分けて、
初めての方でもわかりやすく解説しています。
戸籍を集めるところから、相続人の判断方法まで、順を追って確認していきましょう。
ステップ1:相続が発生したことを確認
相続が始まるタイミングとは
相続は、人が亡くなった時点で開始されます。
役所に死亡届を出すと、「死亡の事実」が公的に記録されます。そのタイミングで、相続に関する手続きができるようになります。
ただし、すぐに手続きを始める必要はありません。まずは落ち着いて、必要な書類をそろえることが大切です。
誰が手続きを進めるべきか
基本的に、相続人となる可能性のある人が手続きを進めます。
家族で話し合って、代表者が動くことが多いですが、第三者(司法書士・行政書士など)に相談することも可能です。
この時点では、まだ相続人がだれかはっきりしていない場合もあります。ですが、相続の対象になる遺産や手続きの内容に影響するため、「誰が調べる役割を担うのか」を早めに決めておくとスムーズです。
ステップ2:亡くなった人の本籍地を調査
相続人を調べるには、まず戸籍を取り寄せる必要があります。
そして、戸籍を請求するには、亡くなった人(被相続人)の本籍地がわかっていなければなりません。
本籍地を知るための方法
本籍地は、普段の生活では意識しないため、知らないことも多いです。確認するには、次のような方法があります。
- 亡くなった人の住民票(除票)を確認する
→ 本籍地が記載されています。 - 家族や親せきに聞いてみる
→ 過去に戸籍を取ったことがあれば、記録が残っていることも。
住民票の除票を取り寄せるには
亡くなった人の住民票(除票)は、最後に住んでいた市区町村の役所で取ることができます。
請求に必要なものは以下のとおりです。
- 申請書(役所にある、またはウェブからダウンロード)
- 請求者の本人確認書類(免許証など)
- 相続関係を証明する書類(必要な場合あり)
- 手数料(300〜400円ほど)
郵送でも請求できますが、数日〜1週間ほどかかることがあります。
ステップ3:出生から死亡までの戸籍をすべて収集
相続人を正しく調べるには、亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集める必要があります。
戸籍をたどれば、結婚・離婚・子ども・養子などの情報がわかり、相続人を確定するための材料になります。
必要な戸籍の種類
- 現在の戸籍(亡くなったときのもの)
- 除籍謄本(過去に籍があった戸籍)
- 改製原戸籍(古い形式の戸籍)
すべての戸籍をそろえることで、家族関係の流れが切れずにつながるようになります。
取り寄せ方
戸籍は、本籍地の市区町村役所で取れます。窓口や郵送、対応していればオンラインでの取得も可能です。
亡くなった人が、転籍や結婚などで本籍を移している場合、戸籍が複数の役所に分かれて保管されていることがあります。
この場合は、次のように進めましょう。
- 今ある戸籍の中に、前の本籍地が書かれている
- その本籍地の役所に、さらに古い戸籍を請求する
- 戸籍が「出生までたどれた」と確認できるまでくり返す
少し時間はかかりますが、一つずつ順番にたどれば必ずつながります。
不安なときは、戸籍を見せながら役所の窓口で相談するのも有効です。
ステップ4:戸籍の記載をもとに家族関係を整理
集めた戸籍をもとに、相続人を調べる前段階として亡くなった人の家族構成を読み取り、関係を整理しておきましょう。
戸籍で確認するポイント
- 配偶者がいるか
- 子どもがいるか(実子・養子・認知含む)
- 子どもがいない場合、親や兄弟姉妹の情報があるか
この3つを確認すれば、相続の対象となる人が見えてきます。
記載の見方
戸籍には、家族に関する情報がこのように記載されています。
- 「妻 ○○と婚姻」→ 配偶者がいる
- 「長女 ○○出生」→ 子どもがいる
- 「養子縁組」→ 養子も相続人の対象
- 「認知」→ 婚外子も対象になる
- 「死亡」や「除籍」→ すでに亡くなっているかどうか確認
情報を図にするとわかりやすい
戸籍の内容をもとに、家族の関係を図や表にしてメモしておくと
次のステップで誰が相続人か判断しやすくなります。
ステップ5:相続人にあたる人を判断
戸籍をもとに家族関係を整理できたら、次は実際に相続人となる人が誰かを判断します。
ここでは、民法で決まっている「法定相続人のルール」にしたがって見ていきます。
相続人の基本ルール(順位と範囲)
相続人になれる人は、次の順番で決まっています。上の順位にいる人がいれば、下の人は相続人になりません。
第1順位:子ども(実子・養子・認知した子を含む)
- 子どもが相続人です
- 子がすでに亡くなっていれば、その孫が相続(代襲相続)
第2順位:父母など直系尊属
- 子どもがいない場合は、父母などが相続人になります
- 両親とも亡くなっている場合、祖父母が対象になることも
第3順位:兄弟姉妹
- 子も両親もいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人になります
- 兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代襲相続することも
※ 配偶者は常に相続人になります(順位とは別枠)
特別な事情があるとき
以下のようなケースでは、注意が必要です。
- 離婚歴があり、前の配偶者との子どもがいる
- 養子縁組している子どもがいる
- 認知した子どもがいる
- 相続人の一部がすでに亡くなっている(代襲相続)
これらもすべて戸籍に記録されていますので、戸籍の内容と相続のルールを照らし合わせることで判断できます。
相続人の具体的なケース
実際に相続人を調べるときは、家族構成によって状況が大きく変わります。
ここでは、よくあるパターンをもとに、相続人がどう決まるのかを具体的に見ていきましょう。
ケース1:配偶者と子どもがいる
家族構成
- 夫が亡くなった
- 妻と子ども2人がいる
相続人
→ 妻と子ども2人の合計3人
※ 子どもは実子でも養子でも認知された子でも、同じように相続人になります。
ケース2:子どもがすでに亡くなっている
家族構成
- 父が亡くなった
- 妻と、すでに亡くなった息子
- 息子の子(孫)がいる
相続人
→ 妻と孫
※ 息子の代わりに孫が相続する「代襲相続」が適用されます。
ケース3:子どもも孫もいない
家族構成
- 女性が亡くなった
- 独身、子どもなし
- 両親が健在
相続人
→ 父と母
※ 子どもがいないときは、両親などの直系尊属が相続人になります。
ケース4:親も子もいない
家族構成
- 独身の男性が亡くなった
- 両親はすでに他界
- 妹がいる
相続人
→ 妹
※ 子も親もいないときは、兄弟姉妹が相続人になります。
ケース5:前妻との子がいる
家族構成
- 男性が再婚し、後妻と暮らしていた
- 前妻との間に子どもが1人いる
相続人
→ 後妻と前妻の子
※ 離婚していても、子どもとの関係が続いていれば相続人になります。
このように、家族構成や過去の事情によって相続人は変わります。
戸籍を見ながら、上記のようなパターンと照らし合わせると、正確に判断しやすくなります。
まとめ
相続人を調べるには、戸籍をもとに家族関係を整理し、法律のルールにしたがって判断する必要があります。
やることは多く見えますが、ひとつずつステップをふんでいけば、確実に進められます。
実際の家族構成に近い例と見比べながら、戸籍をていねいに読みとっていくことが大切です。
わからない点があれば、役所や専門家に相談するのもよい方法です。
落ち着いて、あせらず取り組んでいきましょう。